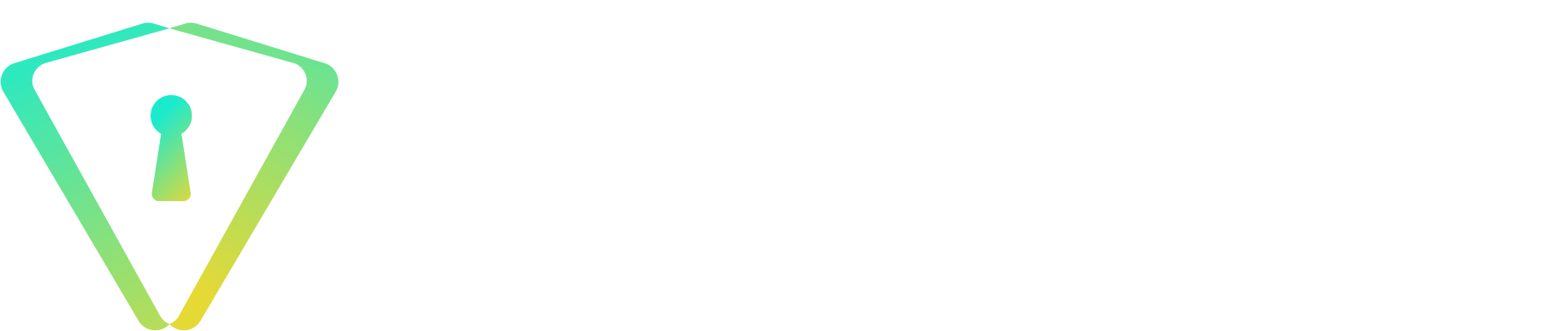ネット風評被害とは?原因と企業が取るべき具体的な対策を解説

取引先や顧客との信頼関係を何よりも重視する経営者にとって、インターネット上に広がる誹謗中傷や根拠のない悪評は頭を悩ませる大きな問題です。
本記事では、ネット風評被害が生まれる背景や実際の被害事例、発生要因から予防策・対処法まで分かりやすくお伝えします。
最後まで読めば、被害を最小限に食い止めて企業の信用を保ち、長期的に揺るがないブランド基盤をつくるためのはっきりした道筋が見えてきます。
ネット風評被害とは
ネット風評被害とは、インターネット上の誤解や根拠のない情報によって、企業や個人の信用が損なわれる状態を指します。
SNSや検索結果で一度広まった情報は長く残り続け、多くの人の目に触れるため、経営に深刻な影響を与えるケースが少なくありません。
風評被害と誹謗中傷の違い
風評被害は事実に基づかないうわさや誤解が広がり、結果として信用を傷つける現象です。一方、誹謗中傷ははっきりと相手を攻撃する意図を持つ発言や書き込みを指します。
例えば「この会社は倒産するらしい」という根拠のないうわさは風評被害であり、「この会社は最低だ」と感情的に非難する投稿は誹謗中傷です。
両者は似ていますが原因や目的が異なるため、対処法も変わってきます。風評被害には正しい情報発信や監視体制の強化が効果的で、悪質な誹謗中傷には削除依頼や法的手段を検討する必要があります。
SNSや検索結果で拡散しやすい特徴
ネット風評被害が広がりやすいのは、SNSや検索結果の仕組みが原因です。SNSは情報がリアルタイムに拡散され、特に感情的な投稿ほど共有されやすい傾向です。
さらに検索エンジンでは一度悪評が掲載されると長期間表示され続け、企業名を調べる人の目に繰り返し触れることになります。
この特性により、誤情報や悪意ある書き込みが瞬時に多くの人へ届き、信頼を失う状況が生まれやすくなっています。つまり、インターネット環境そのものが風評被害を増幅させる要因なのです。
ネット風評被害の原因と事例

ネット風評被害の主な原因は、以下の4つです。
- 誤情報の拡散
- 公式サイトの不適切投稿
- 従業員の不祥事
- 災害時の混乱に伴う誤解
どれもSNSや検索で増幅され、企業の信用に直結する問題となっています。ここでは代表的な原因と実際の事例を示し、再発防止の視点を整理しました。
社内ルールと監視体制を事前に整えることで、被害を小さくすることが可能です。具体例で確認していきましょう。
不正確な情報の拡散
誤情報は、見出しだけが独り歩きしたり、情報拡散が速すぎたりして生まれるケースが多くあります。引用や要約の過程で意味が変わると、事実と異なる印象が定着してしまいます。
公式サイトの不適切投稿
企業の公式アカウントの不適切な投稿も深刻な問題です。不適切な投稿で批判を受け、公式サイトとXで謝罪した事例が複数報告されています。
学校教材メーカーのアーテックは、ある動画への言及が不適切として投稿を削除し、謝罪しました。
参考サイト:小児性愛コンテンツに便乗? 物議の教材メーカーが謝罪「あってはならない」「極めて不適切」
投稿の事前チェックと根拠の明示を徹底すれば、誤解の連鎖を断つことが可能です。一次情報に当たり、見出しではなく本文で数字や出典を確認する姿勢が不可欠です。表現の精度を上げ、記者発表と同じ基準でSNSを運用することが求められます。
従業員の不祥事やバイトテロ
従業員の不祥事やバイトテロは、軽率な行動が動画で拡散し、即座に炎上する現象です。厨房での不衛生行為や悪ふざけ投稿は、ブランドへの信頼を一気に損なう結果を招きます。
回転寿司チェーンのくら寿司では、ごみ箱に捨てた食材を戻す様子が拡散し、会社が謝罪と法的措置検討を発表する事態となりました。社内通報の窓口を決めて、早期に火種を消す体制をつくることも大切です。
参考サイト:くら寿司、“不適切動画”拡散で謝罪 アルバイト店員がごみ箱へ捨てた食材をまな板へ戻す様子が拡散 | ねとらぼ
災害や事故に伴う誤解の拡大
災害や事故が起きると、真偽不明の情報が不足を埋める形で広がることがあります。救助要請を装った虚偽投稿や、公的支援の誤った案内が共有され、現場の混乱を招く事態が発生しています。
東日本大震災では、製油所火災に関する有害物質のうわさが拡散し、後に否定されました。能登半島地震でも、SNS上で救助を求めるデマが投稿され、問題となりました。
企業は公式発表の更新頻度を上げ、一次情報へのリンクを示すと効果的です。誤情報を確認したら、速やかに打ち消し情報を出し、FAQで問い合わせを一本化することが大切です。検索に残る誤解は訂正情報で上書きし、長期的な誤認を防ぐ必要があります。
ネット風評被害が企業に与える影響

ネット風評被害は売上減少や取引先との関係悪化を招き、経営基盤を揺るがす深刻なリスクです。
さらに採用活動への悪影響や社員のモチベーション低下、離職率の上昇につながり、長期的なブランド価値を損ないます。つまり一時的問題ではなく、企業の成長や存続を左右する深刻な問題です。
信用や売上への打撃
ネット検索で企業名や商品を調べた際に悪評が目立つと、多くの顧客は購入や契約に不安を覚えます。信頼を失うと購買意欲は大きく下がり、競合他社へ流れる結果となりやすい状況が生まれます。
例えば、先述のくら寿司では不適切動画が拡散され、既存店売上が前年同月比6.2%減と大きな影響を受けました。
さらに取引先に悪評が伝われば、契約の見送りや解除に発展することもあります。売上減少は短期間では収まらず、風評が長く残ると顧客離れが続き、収益基盤そのものを揺るがす要因です。
特に中小企業にとっては一度の信用失墜が致命傷になりかねず、回復には多大な時間と費用が必要です。このため日常的なネット監視や早期対応が不可欠であり、問題を見過ごせば経営の安定性が大きく損なわれます。信用と売上を守るには、発生直後の迅速な対策と誠実な姿勢が大切です。
参考サイト:https://president.jp/articles//28091?page=1&utm
採用やブランドイメージへの悪影響
求職者は応募前に企業名を検索する傾向が強いため、悪評が上位に表示されると応募意欲を失う結果となります。
特にSNS世代は情報感度が高く、炎上履歴や不祥事が見える企業を避ける傾向が顕著です。その結果、優秀な人材が集まらず採用の質が低下し、長期的な競争力が損なわれる事態になります。
また、ブランドイメージが悪化すれば既存顧客も離れやすくなり、広告や販促活動に投資しても十分な効果を得られません。加えて、社会からの評価が下がると社員が誇りを持てず、モチベーションの低下や離職率の上昇を招くおそれもあります。
こうした影響は企業の成長を阻害し、事業の持続性を脅かす要因です。逆に、普段から正しい情報発信やCSR活動を通じて信頼を築いていれば、悪評の影響を受けにくくなります。採用力とブランド力を守るには、常日頃からの広報戦略と誠実な対応が欠かせません。
ネット風評被害を防ぐための基本対策
風評被害を防ぐ近道は、早期発見と迷わない初動です。毎日のネット監視で異常を察知し、誰が何をするかを決めます。
一次情報で確認し、誤りは訂正と削除を同時に進めます。平時でのポイントは、ルール・連絡網・Q&Aの整備と訓練での定着です。
検索面の第一印象も整え、誤解の広がりを抑えます。広報・法務・現場が連携し、週次で指標を点検しましょう。
ネット監視や社内ルールの整備
監視とルールをセットで運用すれば、被害は小さくできます。拡散前の初動が速くなり、誤解を正しやすいからです。実務では次を徹底します。
- 会社名・商品名・代表者名・誤記の揺れを監視語に登録
- 主要SNS・掲示板・地図・レビューを定点観測し記録
- 異常検知→記録→事実確認→一次対応→再発防止を文書化
- 発信禁止事項と承認フローを明確化し、二重チェックを標準化
- 削除は各プラットフォーム手順で申請し、証拠を保全
- 危機度を3段階に色分けし、担当と期限をチケット(タスク管理票)で管理
検知時間や訂正率をKPIで振り返り、弱点を潰します。加えて、公式サイトで正確なFAQを整え、疑問への先回りする対応も大切です。
検索意図に合わせた見出しと内部リンクで到達を速めます。訂正発信は簡潔に根拠を示し、謝罪と再発防止も明記します。
従業員教育とリスク意識の向上
教育で判断のばらつきを減らせば、炎上は起きにくくなります。全員が同じ初動で動くほど、拡散を抑えられるためです。以下のとおり段階的に進めます。
- 実在の炎上例で影響と損失を示し、自分事化させる
- OKとNGの表現を並べ、迷いやすいグレーを具体例で潰す
- 返信文・社内報告・初動説明の演習を行い、即応を習慣化する
- 管理職にはエスカレーション基準と判断の締切を渡す
- 新人は入社時研修とテスト、誓約をセットで実施する
- 匿名通報と相談の窓口を設け、火種を早く拾い上げる
学習効果を数値で追い、参加率や理解度テストでの可視化が効果的です。社内ポータルに知識や情報を集めて、検索ですぐに使えるようにします。
また、経営層が姿勢を示し、評価と予算を教育の継続に結びつけることも大切です。最後に、定期的な練習と事例の振り返りで知識をアップデートしていきます。
ネット風評被害が起きたときの対応方法
ネット風評被害が発生した際には、初動対応の早さが企業の信用を守る最大の要素となります。
遅れれば誤情報が事実のように広がり、修復に時間と費用がかかります。そのため事実確認・削除依頼・声明発表・法的措置を段階的に行える体制を整えることが不可欠です。
事実確認と削除依頼
ネット上で風評が見つかった場合、最優先すべきは事実確認です。誤情報かどうかを正確に判断し、関連部署や責任者と情報を突き合わせます。内容が虚偽や誇張であると分かれば、削除依頼や訂正要請を迅速に実施します。
具体的には、SNSでは運営会社への違反通報、掲示板や口コミサイトでは管理者への削除要請です。検索エンジンで悪質な記事が表示される場合には、専用フォームから削除申請を行う方法も効果的です。なお、削除依頼は投稿者の反発や拡散を招き、二次炎上に発展する恐れがあります。理由と根拠を簡潔に示し、感情的表現を避けつつ、公開の要否も慎重に判断してください。文面は事前に確認しましょう。
しかし削除が難しいケースも多く、その場合は正しい情報を自社サイトや公式SNSで発信します。検索対策を組み合わせ、正しい情報を利用者の目に届きやすくすることが大切です。
さらに対応の過程を詳細に記録し、後に同様の被害が起きた際の参考資料とします。そうすれば再発防止につながり、迅速で一貫性のある対応が可能です。事実確認と削除依頼は、風評被害対策の出発点であり、信頼回復の第一歩です。
声明発表や法的措置の検討
削除依頼だけでは影響を抑えきれない場合、企業として公式声明を発表する必要があります。
声明では事実を整理し、誠実かつ客観的な表現で誤解を正すことが求められます。発表は公式サイトやSNSで行い、場合によってはプレスリリースの配信も必要です。
感情的な反論は避け、透明性を持って説明することが信頼維持のポイントです。また、悪質な誹謗中傷や営業妨害行為を受けた場合には、法的措置を検討します。具体的には、弁護士と相談し発信者情報開示請求や損害賠償請求を行う方法があります。
法的手段は時間と費用を要しますが、加害者の責任をはっきりさせて抑止力を働かせるのは効果的です。声明発表と法的措置を状況に応じて組み合わせれば、毅然とした姿勢を外部に示せます。
透明性と誠実さを持った情報発信が、風評被害からの回復と長期的なブランド価値維持につながります。
逆SEOや検索対策による信用回復
検索対策は、風評被害からの信用回復を最短で進めるための手段です。悪い評判が目立たないようにして、正しい情報をすぐに見つけてもらえれば、印象がよくなります。
削除が困難な情報も、検索結果の設計次第で影響を弱めることが可能です。重要語のFAQや事例を増やし、構造化データと内部リンクで到達を速めます。指名検索の増加が回復を後押ししてくれます。
逆SEOでネガティブ情報を目立たなくする
逆SEOは、削除が困難なネガ情報の露出を下げる現実的対策となります。理由は、検索の第一印象を公式の正確な情報で満たせるからです。逆SEOを成功させるには、コンテンツ作成・技術改善・継続的な管理の3つの柱を軸に取り組むことが大切です。
【具体的な実施内容】
| 1.コンテンツ作成・改善 | 公式サイトとFAQ・事例・プレスを計画的に増やす |
| 見出しと内部リンクを改善する | |
| 構造化データで理解を助ける仕組みを整える | |
| 地図やレビューの整備も並行して進める | |
| 誤記を含む監視語で検知を早める | |
| 2. 技術面での改善 | サイト速度とモバイル対応を改善し、離脱を抑える |
| ブランド指名クエリを育て、公式導線を強化する |
【進捗管理と運用体制】
| 3.KPI管理 | 上位占有率 |
| クリック率 | |
| 否定記事の平均順位 |
【運用のポイント】
- 不自然な施策は避け、根拠資料と透明な説明で信頼を積み上げる
- 週次でログを分析し、足りない回答は特集ページで補完する
- 法務と広報が連携し、訂正要請と情報更新を同時に進める
- 定例レビューで基準と体制を見直す
ポジティブ情報の発信で信頼を強化する
信頼を強化する近道は、検索利用者を安心させるポジティブ情報を継続的に届けることです。
効果的なポジティブ情報発信には、コンテンツ作成・発信戦略・継続的な改善の3つの要素が不可欠です。
【発信すべきコンテンツ】
| 1-1. 実績・事例の公開 | 顧客の成功事例とレビューの掲載 |
| アフター対応の実績を具体例 | |
| 品質改善や安全対策の進捗報告 | |
| CSRや地域貢献活動の定量的な開示 | |
| 1-2. 信頼性の補強 | 第三者認証や専門家コメントの活用 |
| 受賞歴の掲出 | |
| FAQと内部リンクで疑問に先回りした情報紹介 |
【発信戦略と運用】
| 2. 発信チャネル | 公式サイトとプレスリリース |
| SNS | |
| 動画コンテンツ | |
| 上記を軸にした多面的な展開 | |
| 3. 継続的な改善体制 | 指名検索や再訪率、問い合わせ数をKPIに設定 |
| 編集会議で学びを反映 | |
| 古い情報の整理と重複防止 | |
| 問い合わせ導線の明確化と関係構築への誘導 |
まとめ|ネット風評被害を防ぎ信用を守ろう
ネット風評被害は、放置すると売上や採用に深刻な影響を与えます。まず日常の監視と社内ルールを整え、早期発見を心がけることが不可欠です。
発生時は事実確認を最優先にし、削除依頼と訂正発信を同時に進めていきます。並行して検索対策とポジティブ情報の継続発信で信頼補強に取り組む必要があります。
今日から監視キーワードを設定し、担当と手順を共有しましょう。公式サイトにFAQを整備し、誤解を減らす仕組みも効果的です。
広報・法務・現場が一緒に動ける連絡網があれば、迷わず対応できます。社内教育も継続し、誰もが同じ初動で動けるよう準備しておくことが大切です。